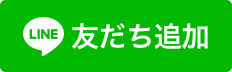ブログ
Blog
患者さんにとって少しでも安心して受診できるように、クリニックの雰囲気などお伝えしていきます。
パニック障害での栄養学ポイント|血糖変動とパニックの関係は?

院長の白岩です。年末になり冷え込みが厳しくなってきましたが、みなさまお元気でしょうか。
北日本は大雪のようで、大変な思いをされている方も多いと思います。お見舞い申し上げます。
今日はクリスマスイブですが、コロナの流行も収まる気配がなく、なかなか外で食べようというのも積極的にはしにくい状況ですし、家でゆっくりされている方も多いかもしれませんね。
さて、今日は前回の「うつ」に続いて「パニック」での栄養療法についてご紹介したいと思います。
パニック障害とは?
パニックはよくある例をあげると、電車やバスやエレベーターのような閉鎖空間などで以下のような症状が出ることを指します。
- 呼吸がしにくくなったり
- 圧迫感や動悸
- めまい、
- 足の震え
- 気が遠くなるような感覚
また、これらの恐怖感から同じような状況に遭遇するとまた同様の発作が出るのではないかと予期不安が起こってきて活動範囲が狭められるような状態です。
症状の大小はありますが、統計的には100人に1~2人くらいが生涯の間に経験することがあるとされており、決して珍しいものではありません。
私の経験では女性の方が多いように感じますが、その理由は定かではありません。
しかし、オーソモレキュラー的に考えるのであれば、鉄不足やタンパク不足がパニックの素因の一つとして考えられます。
パニック障害の際に注目する栄養学的なポイント
さて、パニック障害を栄養療法的なアプローチで考える場合、ポイントになるものは先ほどの鉄やタンパク質ももちろんですが、もう一つ大きな要因として考えられるのが、血糖の問題です。
血糖変動がパニックと関係??
血糖の問題というと普通は糖尿病を考えるかもしれませんが、そうではなく、ここで問題になるのは血糖調節障害や機能性低血糖症です。
あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、わかりやすくいうと、血糖値の上がり下がりが激しい状態のことです。
血糖値の上昇が緩やかな人はインスリン(血糖を低下させる作用のあるホルモン)の出方も緩やかなことが多いですが、急激に血糖が上昇するタイプの人はインスリンもびっくりして大量に出ることがあります。
その分、血糖の下がり方も急激になるため、今度はまるで低血糖を起こしたような状況になるのです。
そうすると、体は低血糖状態は生命の危機と感じてしまい、アドレナリンやステロイドのようなストレスホルモンをたくさん出し、交感神経を強めて危機を脱しようとします。
その際、動悸や発汗などの自律神経の乱れが生じやすくなります。
これがパニック発作のように感じやすくなる一つの要因です。
普段からよく甘いものを食べる方、空腹感を強く感じやすい方、食事の後に眠くなりやすい方、太りやすい方、眠りが浅いと感じている方…
血糖が乱れやすいこのような様々な特徴を感じている方は注意が必要かもしれません。
食べ方一つを変えるだけでパニックを予防できれば、薬を使わずに済む可能性もありますので、血糖変動が気になる方は一度検査を受けてみるのもいいかもしれません。
ラエティスクリニック本町〒541-0053 大阪市中央区本町3-1-2 イワタニ第三ビル4F
心療内科
TEL:06-4705-7388
FAX:06-4705-7389
| 診療時間 |
|
|---|---|
|
|
- ※1:木曜日の午後は15:00~18:30の診療となります。
- ※2:土曜日の午前は10:00~13:30の診療となります。
- ※3:土曜日の午後は訪問診療を行っております。
婦人科
TEL:06-4705-7377
FAX:06-4705-7389
| 診療時間 |
|
|---|---|
|
|
|
|
- ※:土曜日の午前は10:00~13:30の診療となります。