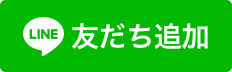ブログ
Blog
患者さんにとって少しでも安心して受診できるように、クリニックの雰囲気などお伝えしていきます。
生理不順はストレスが原因?身体に与える影響と改善方法を解説

女性にとって大きな悩みの種である生理不順はさまざまな原因が考えられますが、ストレスが関係しているケースは少なくありません。
そこで本記事では、ストレスが原因で生理不順となる理由について、詳しく解説します。
あわせて、生理不順の改善方法を心療内科・婦人科を併設しているラエティスクリニックが解説するので、「もしかしたらストレスが原因かも…」と悩まれている方は参考にしてください。
Contents
ストレスが原因による生理不順の種類
患者様によって症状は異なりますが、ストレスが原因による生理不順は次のような症状が挙げられます。
←横方向へスライドできます→
| 症状 | 特徴 |
| 無月経 | 3ヶ月以上、生理がこない状態 |
| 頻発(ひんぱつ)月経 | 生理周期が24日未満と短い状態 |
| 稀発(きはつ)月経 | 生理周期が39日以上と長くなる状態 |
| 過少(かしょう)月経 | 1周期あたりの出血量が30ml未満と、極端に少ない状態 |
| 過多(かた)月経 | 1周期あたりの出血量が80ml未満と、極端に多い状態 |
ストレスと生理不順の関係性
ストレスは、生理不順に大きく関係しており、特にストレスがホルモンへ影響を与えることが大きな原因として考えられます。
生理とホルモンの関係性
生理(月経)とホルモンの関係性は以下のとおりです。
- 卵胞期に性腺刺激ホルモン(GnRH)が分泌される
- 卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体形成ホルモン(LH)の分泌を促し、卵胞が形成される
- 卵胞からエストロゲン※1が分泌され、卵子の成熟・子宮内膜の肉厚化が起きる
- 排卵期(エストロゲン分泌のピーク)にLHの影響で排卵が起きる
- 排卵後、プロゲステロン※1というホルモンの分泌によって卵子が着床しやすくなる
- 着床しないことで子宮内膜は役目を終えて剥がれおち、生理(月経)が起きる
このように、生理はホルモンと密接な関わりを持っています。
※1:女性ホルモンの総称
ストレスによる生理への影響
ストレスを感じると、脳はCRHと呼ばれる副腎皮質刺激ホルモンを分泌し、卵胞期に分泌されるべき性腺刺激ホルモン(GnRH)が抑制されます。
その結果、卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体形成ホルモン(LH)も減少し、エストロゲンやプロゲステロンも抑制され、周期の乱れや無月経といった生理不順が起こります。
生理不順が身体に与える影響
生理不順が長く続いてしまった場合、体のさまざまな部分へ悪い影響を与える恐れがあるため、注意が必要です。
生理不順が身体へ与える影響について解説します。
卵巣機能への影響
生理不順や無月経が長期間続く場合、卵巣機能が低下して妊娠しにくい身体になる場合があります。
また、無月経までに至っていない方でも、ホルモンバランスの崩れなどが原因で、将来的に無月経となってしまう可能性もあります。
骨粗しょう症になるリスク増加
生理と密接な関係にある女性ホルモンは、骨密度を保つ働きも持ち合わせています。
そのため、女性ホルモンが減少することで骨が脆くなるなど、骨粗しょう症のリスクを高めます。
貧血
生理不順のなかでも、頻発月経や過多月経の症状の場合、体内の血液量が不足して鉄欠乏性貧血を引き起こすケースは少なくありません。
貧血が起きると次のような症状が現れやすく、日常生活にも影響を与える可能性があるため注意が必要です。
- 疲労感、倦怠感
- めまい、立ちくらみ
- 動機、息切れ
- 頭痛、耳鳴り など
その他の症状
その他の症状として、ホルモンバランスの乱れが原因で次のような「心に対する症状」が現れることもあります。
- イライラ
- 気分の落ち込み
- 集中力の低下 など
上記のような症状が現れると、学校や仕事、日常生活にも影響が及び、症状がさらに悪化する可能性もあるため注意が必要です。
生理不順の改善方法
生理不順は、ご自身によるセルフケアである程度改善できる場合があります。
ただし、あくまでもセルフケアのため、一定期間試しても症状が改善されない場合は専門医へ相談するようにしましょう。
ストレスの解消
深呼吸や瞑想、何もしない時間を作るなど、リラックスできる工夫をしてみましょう。
その他にも、趣味の時間に没頭したり、散歩で気分転換をしてみるなど、ストレスをできるだけ溜め込まないようにすることが大切です。
規則正しい生活習慣を身につける
生活習慣を見直し、寝る時間と起きる時間を決めるなど、規則正しい生活を身につけることも大切です。
規則正しい生活を送ることで体内時計が整えられ、ホルモンバランスの安定が図れ、生理周期の乱れの改善が期待できます。
生理不順改善に必要な栄養素を摂取する
生活習慣とともに、食生活の見直しをすることも大切です。
特に、次のような女性ホルモンに必要とされている栄養素を積極的に摂取することでホルモンバランスの乱れが改善できます。
←横方向へスライドできます→
| 栄養素と効果 | 含まれる食材 |
| 大豆イソフラボン (エストロゲンと同様の働きをする) | 大豆製品(豆腐・納豆・豆乳 など) |
| ビタミンB郡 (女性ホルモンの合成を助ける) | レバー、魚、バナナ、緑黄色野菜 など |
| ビタミンE (卵巣の働きを助ける) | ナッツ類、ほうれん草、カボチャ など |
| ミネラル (女性ホルモンのサポート、健康維持) | レバー、赤身肉、ひじき、ナッツ類、大豆製品、牡蠣 など |
| タンパク質 (身体を作るための主原料) | 肉、魚、卵、乳製品、大豆製品 など |
ラエティスクリニックでは、栄養療法も取り入れております。
女性特有のお悩みにしっかりと耳を傾け、様々な検査を通じて生活習慣のアドバイスや必要とする栄養素のご提案をさせていただいております。
まとめ
生理不順は、身体だけでなく心にも影響を与えるため、なるべく早めの症状改善が必要です。
しかし、「セルフケアだけだと続かない」「症状がなかなか改善しない」と諦めてしまわれる患者様も少なくありません。
ラエティスクリニックでは、このようなお悩みにしっかり寄り添い、生理不順を改善するためのお手伝いをさせていただいております。
ただ症状を伺って薬を処方するのではなく、「薬の卒業」をゴールとした症状へのアプローチをご提案させていただきます。
生理不順に悩み、「自分らしい日常生活を送りたい」とお考えの方は、まずはお気軽にラエティスクリニックまでご相談ください。
ラエティスクリニック本町〒541-0053 大阪市中央区本町3-1-2 イワタニ第三ビル4F
心療内科
TEL:06-4705-7388
FAX:06-4705-7389
| 診療時間 |
|
|---|---|
|
|
- ※1:木曜日の午後は15:00~18:30の診療となります。
- ※2:土曜日の午前は10:00~13:30の診療となります。
- ※3:土曜日の午後は訪問診療を行っております。
婦人科
TEL:06-4705-7377
FAX:06-4705-7389
| 診療時間 |
|
|---|---|
|
|
|
|
- ※:土曜日の午前は10:00~13:30の診療となります。