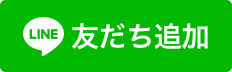お知らせ
Information
2025.10.24
不安障害の治し方|根本からアプローチする栄養療法とは
誰もが抱える何かしらの不安。
しかし、なかには過度な不安や恐怖が原因となって心身にさまざまな症状が現れ、不安障害として日常生活にも支障をきたしてしまう方もいらっしゃいます。
そこで本記事では、不安障害の定義とともに根本から改善する方法について、心と身体の不調へ栄養療法でアプローチするラエティスクリニック本町が詳しく解説します。
不安障害を改善し、「自分らしく明るく日常生活を送りたい」と悩まれている方の参考になれば幸いです。
Contents
治し方の前に不安障害を再定義
不安障害は、以下の3つの障害の総称です。
- 全般性不安障害(GAD)
- パニック障害
- 社交不安障害(SAD)
すでにご存じの方もいらっしゃるかとは思いますが、改めて各障害の特徴や症状について再確認をしていきましょう。
←横方向へスライドできます→
| 項目 | 全般性不安障害(GAD) | パニック障害 | 社交不安障害(SAD) |
| 主な特徴 | 日常生活全般に対し、過剰な不安や心配が続く | 突然強い恐怖や動悸などの発作(パニック発作)が繰り返される | 人前での評価や他者からの視線に対し、強い恐怖心や緊張感を抱く |
| 不安の対象 | さまざまな状況・将来・健康など特定の出来事に限らない | パニック発作そのものや再発への恐怖 | 他人の注目・批判・恥をかく状況(会話・発表など) |
| 発作の有無 | なし (慢性的な不安が続く) | あり (突発的で激しい) | 特定の社会的状況でのみ出現する |
| 主な身体症状 | 筋緊張、疲労感、集中困難、睡眠障害、動悸 | 動悸、息苦しさ、めまい、発汗、死の恐怖 | 顔の赤面、震え、発汗、動悸、吐き気など |
| 発症のきっかけ | ストレス、性格傾向(心配性)、生活の変化 | 強いストレス、遺伝、体調変化など | 過去の失敗経験、対人不安、性格傾向(内向的) |
| 発作の持続時間 | 慢性的 (数か月以上続く) | 数分〜数十分程度 | 状況に応じて一時的 (その場面でのみ) |
| 行動への影響 | 常に緊張して集中力が下がる、疲れやすい | 外出や乗り物などを避けるようになる (広場恐怖を伴う場合もある) | 人前での行動を避ける、学校・職場での支障 |
| よく併発する症状・疾患 | うつ病、睡眠障害、身体症状症 | 広場恐怖、うつ病 | うつ病、回避性人格傾向 |
| 治療法 | 認知行動療法(CBT)、SSRIなどの抗不安薬 | CBT、SSRI、発作時の短期的抗不安薬 | CBT(暴露療法含む)、SSRI |
| 経過 | 長期にわたり慢性化する傾向がある | 発作を避ける行動により、慢性化する場合もある | 徐々に回避行動が強まり、慢性化しやすい |
従来の不安障害の治し方とその限界
従来の不安障害の治療法として、薬物療法と精神療法を組み合わせた治療が一般的ですが、これらの治療には限界があります。
不安障害に対して行われる一般的な治療法、そしてなぜ限界といわれるのかについて解説します。
標準的な治療法
不安障害の一般的な治療法として、抗不安薬や抗うつ薬などを用いた薬物療法、そして心理療法として認知行動療法(CBT)が選択されるケースがほとんどです。
なぜ薬での治療が難しいのか?
抗不安薬や抗うつ薬は、あくまでも「症状を抑えるための対症療法」でしかなく、原因の根本的な解決策にはなりません。
また、認知行動療法についても「課題を乗り越えなければ」「考え方を変えなきゃ」という精神的負担を抑えこむエネルギーが足りないことにより、却って逆効果になってしまうケースもあります。
不安障害に根本からアプローチする栄養療法
不安障害は、心の問題という単純なものではなく、脳内神経伝達物質のバランスの乱れが大きく関与しています。
このことから、ラエティスクリニック本町では神経伝達物質の材料となる栄養の摂取に焦点を当て、栄養療法によって根本からアプローチしております。
栄養不足や炎症、体内の酸化と抗酸化のバランスが崩れることで生じる酸化ストレスなど、栄養バランスの乱れにはさまざまな要因が考えられるため、血液検査などで患者様一人ひとりの状態を確認させていただき、個別に栄養指導をさせていただきます。
従来の治療は「症状を緩和しているだけ」であり、薬の服用などを止めてしまうと元に戻ってしまいます。
一方で、栄養療法なら中長期的な視点で治療を続けていただくことにより、薬に頼らなくても発作が起こりにくくなる身体に造り替えることが可能です。
不安障害を悪化させないためにできること
不安障害は、不足する栄養の摂取を含む生活習慣の見直しとともに、以下の点を心がけることで症状の悪化を防ぐ効果が期待できます。
- 規則正しい睡眠の確保:
就寝・起床時間を一定にし、体内時計を整えることで自律神経を安定させる。
寝る前の1時間はスマホやPCの画面(ブルーライト)を見ないようにし、脳の休息を優先する。 - 適度な運動の習慣化:
ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、気分を安定させるセロトニンの分泌を促し、運動を習慣化することで自律神経の調整にも役立つ。
ストレスを溜めることが何よりもよくないので、散歩のような無理のない範囲から始めることが大切。
まとめ
誰もが抱える不安が悪化し不安障害となると、どのタイミングで発作が起こるかわからなかったり、人前に出ることが怖くなったりして日常生活に大きな支障をきたします。
ラエティスクリニック本町では、従来の治療法では限界があり、神経伝達物質を作る栄養が不足しているという考えから、栄養療法によって不安障害へアプローチをいたします。
患者様の症状によっては薬を処方させていただくこともありますが、不足する栄養を食事やサプリメントによってしっかり摂取していただき、最終的には「薬に頼らなくとも発作が起こりにくい身体」を造っていただくためのサポートをさせていただきます。
不安障害を乗り越え、「自分らしく活き活きと毎日を過ごしたい」とお考えの方は、まずはお気軽にラエティスクリニック本町までご相談ください。
ラエティスクリニック本町〒541-0053 大阪市中央区本町3-1-2 イワタニ第三ビル4F
心療内科
TEL:06-4705-7388
FAX:06-4705-7389
| 診療時間 |
|
|---|---|
|
|
- ※1:木曜日の午後は15:00~18:30の診療となります。
- ※2:土曜日の午前は10:00~13:30の診療となります。
- ※3:土曜日の午後は訪問診療を行っております。
婦人科
TEL:06-4705-7377
FAX:06-4705-7389
| 診療時間 |
|
|---|---|
|
|
|
|
- ※:土曜日の午前は10:00~13:30の診療となります。